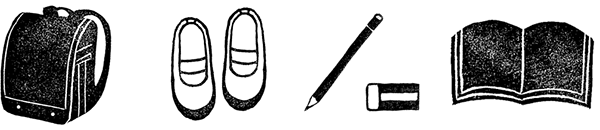特別支援教育
特別支援教育コース
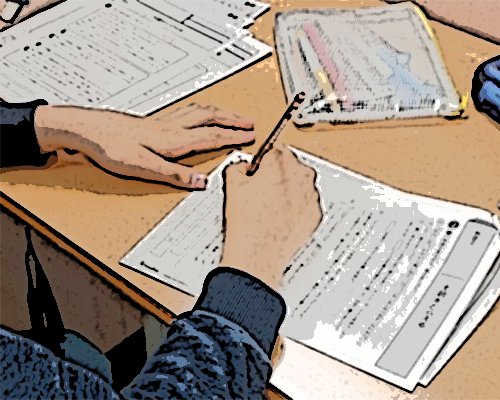
子どもたちは、まさに十人十色、百人百様。ありのままで多様です。
そうした一人ひとりに、しっかりと向き合いたいという願望が、本格的に特別支援教育を学ぶきっかけとなりました。
教える側が学ぶこと、知ること、気付くことにより手立てが見つかります。
「私たちの教え方で学べない子には その子の学び方で教えよう」
これは、日本LD学会でご活躍の上野一彦先生の箴言です。
特別支援教育士の資格を取得した今も、学びへの熱量は増すばかりです。
ご一緒に、お子様の成長に関らせて頂ければ幸いです。
【大切なこと】
発達障がいは、本人の努力不足ではありません。原因は脳の機能障がいであるため、見かけだけでは分かりにくく、本人にも自覚がなく、保護者も支援者も知識がないと正しく理解できないのです。よって、行動の特徴を観察することでその傾向を掴むしかありません。
つまり「正しい知識」があってはじめて「正しい理解」ができ、「正しい支援」に結びつくと考えます。

特別支援教育事例
Aさん(高校生男子)
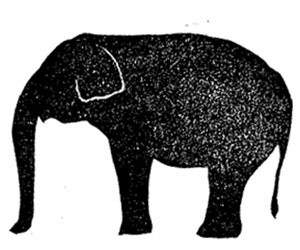
Bさん(小学生男子)
入塾2年目。大人が使うレベルの言葉を使って反発する。うまくいかないと集中力が途切れ、ノートを破いたり、椅子を蹴ったり、毒舌を吐く。しばらくすると、わが身を反省し、元に戻ろうとするやさしさとバネを見せる。
十分にコミュニケーションを取ること、要望は叶える前提で、事前に約束をし、暴走の歯止めにすることを基本にしている。また、学校の担任の先生とも保護者を介して連携。宿題を共有することで、進度の確認と見守りの輪の拡大を図っている。

Cさん(小学生男子)

「ことばの学校」を受講目的に入塾して3年。読んだ本は100冊に及ぶ。その間、漢字検定9級合格、算数検定は10級を勝ち取り、次は9級にチャレンジ予定。ご父母の地道なサポートあっての成長を感じる。
読書の後のワークの取り組みは、音読を推進して、語彙や論理力を獲得するコーナーとしている。
Dさん(小学生男子)
次から次に考えが浮かび口に出すので言わば朗らか。決して否定せず彼持ち前の向学心に誘導。
算数は良好だが、国語が課題。「ことばの学校」と「論理エンジンキッズ」、英語を受講。
色彩感覚も優れ、カラフルな色使いで楽しませてくれる。正直なので宿題の加減に注意している。

Eさん(中学生女子)

小学高学年より不登校に。集団は苦手だが勉強は続けたいとアゴラ生として週に2回通塾している。
自分の意志を強く持ち、自分磨きを忘れない。思いの表現は未だすることは難しいが意思表示はできる。
彼女の表に出ない思いを信じて、アゴラが居心地の良いところになるよう声掛けを励行している。
塾長と特別支援教育
Q, 特別支援教育を学んだきっかけは?
A: 15年ほど前、あるお母様との出会いがきっかけです。
わが子の障がいを受け入れるために、様々な本を読んだり、セミナーに参加したりして、当時小学生だった男児の子育てに奮闘されていました。その姿に感銘を受け、私も人間とは?多様性とは?など、多くの触発を受け、もっと学びたいと思いました。
Q, 発達障害の凸凹を数値化するWISC(ウィスク)を受けましたが、この結果はお見せしたほうが良いですか?
A: 特別支援教育士(S.E.N.S.=センス)という資格を取得するにあたり、一通りの心理検査について学んでおります。
もちろんWISCも含まれていますので、検査結果を共有させていただけますでしょうか。お子様の対応に生かすひとつの手立てとして、科学的な側面も生かしたいと思います。
Q, 今は小学生ですが、中学、高校、その先の進路を考えると不安になります。
A: 先が読めない「未来」にばかり目を向けていると確かに不安になりがちですよね。なるべく「未来」ではなく「今」に目を向けましょう。今に目を向けるといろいろな知恵が湧いてきます。
できれば、相談や気持ちを分かち合える仲間を作る事を強くお勧めします。情報キャッチのアンテナを立てつつ、親も支援者も子どものプラス面を見ていく”自分変革”に共に取り組んでいきたいと思います。
Q, アゴラで「特別支援教育」を掲げる理由は何ですか?
A,正直自分に如何ほどのことができるのか恐れる気持ちもあります。しかしこの分野は未だ発展途上にあり、先ずは「志ありき」だとハラを決めました。相模原にも大貢献されている星山麻木先生の後ろ姿に学び、過去20年の進学塾の経験もここぞと活かしながら、みなさまのお役に立ちたいと考えております。
所属機関
特別支援教育士資格認定協会
日本LD学会
子どもの発達科学研究所